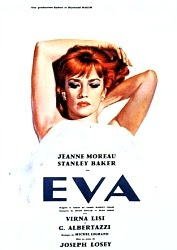てんで出鱈目なストーリー展開なのに、ずっと目が離せません。
活気のあるパリの中心地から殺風景な再開発中の地区まで、すべて屋外で撮影されています。街中の建物、フランス車があふれる道路、ロータリーのライオンのオブジェ、石の階段、郊外の廃墟、そこに隣接する荒涼とした集合住宅。どの風景もたいへん魅力的です。1980年のパリの記録にもなっています。
ちなみに、全場面を屋外で撮影しているせいか、ビュル・オジェ扮する主人公は閉所恐怖症という設定です。閉所恐怖症という人物設定だから屋外の場面が多くなった、という通常の発想ではないでしょう。
映像はDVDで観てもざらざらした質感です。16ミリキャメラで撮影されたのでしょうか。軽量のキャメラは屋外で機動的に撮影するのに便利なはず。また、コントラストの低いざらざらした映像は、夢の中のできごとのような本作の雰囲気に合っています。
イカれた娘を演じるパスカル・オジェにも目が釘付けです。ギリシャ彫刻のように端正な顔立ちにすらりとしたスタイル。いくどか披露される空手の所作は優雅です。
ビュル・オジェが唐突に射殺された後、パスカル・オジェが謎の男に空手で挑むラストシーン。いつのまにか男が指導モードに入って、二人の演武が延々と長回しで捉えられます。画面はときどき十字線が入ったキャメラのファインダーとなり、あたかも記録映画。パスカル・オジェはこの作品の数年後に亡くなったので、この場面は本当に記録になってしまったわけですが。
ビュル・オジェとパスカル・オジェは本当の母娘です。それにしては似ていないなあ。お母さんのビュル・オジェは、今の坂口良子に似ていると家人が申しておりました。オリヴェイラの「
夜顔」では主役、リヴェットの最新作「
ランジェ公爵夫人」にも出演していました。
このゆるゆるした映画は映画館で観てみたかった。映画館で映画を観る幸福は、暗闇と大きなスクリーンによって映画の中に包まれてしまうことにあります。以前は、映画館の大小を問わずつねに一番前の席に陣取りました。今では視界の8割くらいをスクリーンが占める位置に座ります。
そういえば、中学生のころ、シネラマの大スクリーンが売り物だったテアトル東京でも意地を張って最前列に座ったことがあります。これはさすがに辛かった。スクリーンの半分くらいしか視界に収まらなかったので。